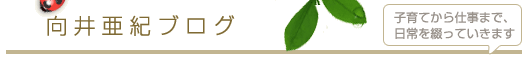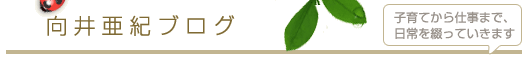|
|
 |
| 日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
|
|
|
|
1 |
2 |
| 3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
| 17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
| 24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
| 最新の記事 |
 |
|
|
 |
 |
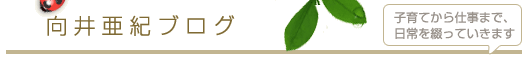

 「会津伝統野菜いろいろ」 「会津伝統野菜いろいろ」
2017年9月12日
 こんなにたくさんあるんです。 こんなにたくさんあるんです。
生物農芸学科の向井、中退ではありますが、めっさ心が踊りますわー
実はこの資料、2年前の福島ツアーの際にいただいたものなので、私のメモがワサワサ書き込んであって、ちょっとお恥ずかしいのですが。
右下の写真が余蒔胡瓜です。
国のシードバンクから種をもらい、長谷川さんが復活させた宝物です
よくぞ復活してくれました。
よくぞ復活させてくださいました。
品種改良は悪いことではありませんが、原種は絶対に残しておくべきです。
植物が長い長い時間をかけて編み出してきた命の技には、とてつもないエネルギーが秘められているはず。
形が揃わないから、見た目の印象が薄いから、手間がかかるから等々、人間からの都合だけで考えてしまったら、取り返しのつかないことが起こるような気がしてなりません。
農林高校の生徒さんたちの努力も本当に素晴らしいので、会津伝統野菜、これから必ず来ますよ!
是非、覚えておいてくださいませ。
|

 「余蒔胡瓜@髙田家」 「余蒔胡瓜@髙田家」
2017年9月12日
 味が染み込みやすいよう、少し皮を剥きつつ。 味が染み込みやすいよう、少し皮を剥きつつ。
まな板の上でゴンゴン叩き、塩と白醤油、ほんの少しの胡麻油で和えただけです。
美味しすぎーる。
|

 「会津農林高校にて」 「会津農林高校にて」
2017年9月12日
 「人と種をつなぐ会津伝統野菜」会長の長谷川純一さんから、会津に伝わる伝統野菜について、教えてもらいました。 「人と種をつなぐ会津伝統野菜」会長の長谷川純一さんから、会津に伝わる伝統野菜について、教えてもらいました。
山に囲まれた会津盆地には、古くから伝わる独特な作物があり、その大切な種と農法を守り伝えていくためにご尽力なさっている方なんです。
活動の一つとして、会津農林高校の生徒たちと一緒に、会津伝統野菜を作り、その素晴らしさを広くアピールするために、様々なイベントを行なっているそうです。
こちらは、会津余蒔(よまき)胡瓜。
ここまで大きく成長させるのは、種を取るためなのだとか。
美味しく食べたいときは、私たちがよく見る胡瓜と同じくらいの長さでいただきます。
が、違うのは太さ!
皮の色が薄く、瓜のように太いので、見た目からの「美味しそう予感」はあまりないんですよね(笑)。
が、これが本っ当に美味しいんです。保証します。
瑞々しく、歯ざわりが軽やかで、‥我家では、万里結太が競い合って食べますねー(^-^)v
種を取るために、しっかり実らせて。
丁寧に種を集め、乾かし、季節を待って、また会津の豊かな土に植えて。
農作物は本来、そうして繋いでいかなくてはならないものだったはず。
長谷川さんは先人たちの教えを、もう一度取り戻すために、真っ黒に日焼けしながら真摯に頑張っていらっしゃいます。
|

 「そして、乾杯🍻」 「そして、乾杯🍻」
2017年9月12日
 冷えたビール、そして福島の日本酒。 冷えたビール、そして福島の日本酒。
たまりません。
|

 「磐梯熱海温泉 華の湯にて」 「磐梯熱海温泉 華の湯にて」
2017年9月12日
 お湯自慢、お料理自慢のお宿へ行きました。 お湯自慢、お料理自慢のお宿へ行きました。
ふくしまの食を体感する旅として、こちらでは齋藤正大シェフにお話を伺いました。
震災までは、華の湯に泊まりに来てくださるお客さんに、非日常を楽しんでいただけるよう、アレコレ工夫してお料理を作っていた花形シェフ、齋藤さんでしたが。
震災が起き、磐梯熱海への原発事故の影響はなかったものの、風評被害により、お客さんがまったく訪れなくなってしまった大型温泉宿。
‥その静かすぎる厨房に、呆然と佇むお姿が目に浮かびます。
復興工事等のための宿泊施設として、現場で泥だらけになって働く皆さんが、華の湯に大勢泊まるようになっていた時期、齋藤さんは、「皆さんの明日のために、しっかりと料理を作ろう。食べたあとに身体が温かくなるような、疲れが軽くなって未来を明るく思い描けるような、そんな料理じゃなければ意味がない」と、ご自分の価値観が大きく変わっていくのを感じたそうです。
地産地消にこだわり、身体に優しいお料理を、今も美味しく作り続けている齋藤さん。
普段は照れ屋さんで、あまりお話なさらないタイプのようですが、お料理にのお話になると、このハジける笑顔! ステキです!
こちらのパネルは、宿泊の子どもさんたちに参加してもらうお料理教室のポスター。
子どもたちに地元で採れた食材を使って調理してもらい、それを一緒にすべて食べるのだそうです。
本当のご馳走、ですね。
子どもたちはもちろん、私たちも、食べることの意味をもう一度考え直しておけば、未来はもっと明るくなりますね。
|
 |
 |
 |